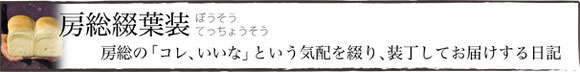今月号は「房総おいしい御醤油の会」でお世話になっている、芝山糀店の「糀王子」こと及川涼介さんにご登場いただきました。今、自宅の古民家「にいさんち」に会の諸味を保管しており、時折アドバイスをいただいていました。
「おばあちゃ~ん、1万6千円ね」
お客さんの会計を済ませて祖母、芝山博子さんに呼びかける涼介さん。弱冠25歳のその声には若いフレッシュさが漂いますが、ひとたび糀室や諸味を前にした時、その眼はギラリと鋭さを増します(その涼介さんの眼差しは、ぜひ本誌でご覧下さい)。
取材では糀の原料となる米を蒸し上げたところから撮影に入らせていただきました。ひんやりした三和土の向こうの部屋にゆくと、蒸し器からもうもうと蒸気が溢れ出ているところでした。スコップで掘り出した蒸米を筵(むしろ)に手際よく広げていきます。

「むしろを作る農家さんがいなくなったね。
今は農協から買ってます」
と博子さん。とはいえ、筵を使っている場面に遭遇できただけでもこちらは嬉しいです。博子さんと涼介さんは解説しながらも忙しなく蒸米をかき回します。
「冷まさないまま種糀を播いても熱さで死んじゃうんです。
米に傷を付ける意味もあります」
と、涼介さん。傷があれば糀菌は米の中に入り込みやすくなるわけですね。そんな話をしつつ、よく見ると博子さんはかき回しながらも米に付いた藁(わら)やゴミを取り除いているのです。こんな細やかな配慮までされているとは正直驚きました。

「黒いお米は別にまた仕込みます。
黒いお米は混ぜたりはしやすい、さらさらしてて。
でも菌がつきにくくて苦労します」
と、分搗き米でも仕込むことがあるそうです。
基本的に農家の方から米を持ち込んでもらい、個々の希望に応じて糀や味噌を作り上げているのです。そんな昔ながらのオーダーメイドな商いのスタイルが、まだこの鴨川の地で息づいていたのです。
蒸米に種糀をまき、今度は蒸米が冷え過ぎないうちに、糀室まで筵ごと運びます。
「でも暑過ぎてもだめなんです。
この後の工程がずれちゃうんです
30度ちょっとがいいのかな」
ちょっとでも糀菌にとって心地の良い環境から外れてしまうと、固まったり(ダマのようになる)、花(糀菌が繁殖した状態が花のように見える)が出過ぎたりします。
「これははぜ(菌が入り込んで白くなること)過ぎ、
固くなっちゃった。
昨晩、ストーブを弱にしてたんですが
付けっぱなしにしてたんです。
(昨年の)大雪の日の記憶があったからな~」
温度管理に悔やむ涼介さん。
「同じようにやったつもりでも、
(出来上がりが)毎回違うんです。
米、温度、湿度によっても違います。
種の量とかで調整したりもしますけど、
先が見えない、
未知の段階を進んでいるのが面白い。
昨日はなかなかはぜてくれなかったり。
菌自体が生き物ですから」
気持ちを改めるようにそう言って、前日室に入れた米糀(蒸米に種糀をまいた状態のもの)を両手で掬(すく)うようにして、ムラがなくなるよう何度もかき回します。ザッ、ザッ、ザッという、一定のリズム。糀室に、ただ響き渡るその旋律は、子守唄のような安心感が漂っているのです。
蒸しあげてから室に入れて3日目で外に出し、糀が出来上がります(持込みで糀づくりをお願いする時は一週間程度余裕をみます)。


涼介さんは、
「重労働なところは僕が中心に。
会計などはおばあちゃんメイン」
と、84になる博子さんを気遣いつつ、祖母から孫へ、その技術を受け継がんとされています。芝山糀店の創業年は定かではありませんが、「慶応」らしい文字が窺える糀蓋が残されていることから、江戸時代には店があった可能性があります。明治時代には間違いなく営業はしており、今も工房の一部は大正時代のままだそうです。
「まちに糀屋が必ず1軒はあったもの。
鴨川にも4軒はありましたよ」
と振り返る博子さん。現在は芝山糀店を入れて2軒に減ってしましました。芝山糀店は元々は糀の専門店でしたが、
「昭和30年代から味噌の加工依頼が増えたんです。
農家の方が働きに出るようになって。
兼業化ですね」
これまで農家が各家々で行っていた味噌造りを、芝山糀店でも担うようになりました。今でも大豆を持込んでもらい味噌を仕込んでいるほか、工房で小売りもされており、通常タイプと「糀多め」を購入することができます。
また、私が訪ねた時は甘酒の販売もされていました。酒粕を溶かした甘酒ではなく、糀をお湯で割った甘酒は、アルコールの残り香、のようなツンとした香りはなく、実にまあるい口当たり。デンプンを糀菌が糖化した、その米の甘さはすっと身体に溶けてゆくかのような柔らかさなのです。あまりの飲みやすさに感動していると、嬉しそうに博子さんが
「好きな人はそのまま飲んじゃうの、ちょっと甘いけどね。
でも砂糖はまったく入っていないの」
甘酒のストレート、自宅でも味わってみましたが、甘党の私はクイクイいけちゃちゃいます(飲み過ぎ注意・笑)。なにせべたっとした甘さじゃない、嫌な後味がないのですから。

「甘酒は1週間は持ちますよ。
だんだん酸味が出てきますが、
重曹をちょっとだけいれると酸味が採れます、
ほんのちょっとね」
と博子さんがおばあちゃんの知恵を披露すると、涼介さんはすかざす、
「アルカリと酸が結合するんですね」
と、明晰に解説を加えます(さすが農大醸造課卒です・笑)。この、孫と祖母、硬軟うまく入り交じった糀造りの現場が、今の芝山糀店の際立たせているのかもしれません。
居間で甘酒を戴いていると、不意に涼介さんが、
「実は『甘酒カフェ』をやりたいんです」
と呟きます。
「ちゃんと糀の甘酒も知ってもらいたいんです。
糀を知ってもらう手段です。
アルコールはない、
酒粕を溶かして作ったものとは違うこと、などですね。
1杯を飲んでもらうと分かる。
その飲んでもらうまでがたいへんなんですが」
それに元々、糀屋の夏の副業として甘酒があったようです」
涼介さんが目指すものはそれだけじゃありません。
現在、国産丸大豆と麦に糀をまいて作った醤油糀から醤油を試作していますが、麦ではなく米を使った醤油糀で「米醤油」も試作されているのです。

「米糀と味噌だけなら、
ずっとあったものをやるだけじゃないですか。
ひとつ、新しい事したいなって思うんです。
でも、お酒や酢は難しい。
このような施設なら、醤油でいこうと。
手づくり醤油は本当においしいんです。
そういうことを伝えていけたらと思うんです」
涼介さんの語気が強まると、博子さんが、
「大豆と糀を分けて欲しいって、
東京の方から申込いただくんですよ。
自分で仕込みたいんですって。
都会に近い糀屋さんは、
団地の人に頼まれてみんなで仕込むとか、
そういう注文を受けるそうね」
そんな需要を物腰柔らかに教えてくれる。そのやさしいおばあちゃんに連れられて、1歳の頃から糀室で作業を見ていた。兄弟の中でも一番関心を示していたといいます。
「ある日、お客さんで、
十何樽もの味噌を買ってくれるお客さんがいたんです。
そのお客さんに言われたんです。
『この代で糀屋さんが終わると淋しいね』と。
その時、スイッチが入った」
中学の時には後を継ぐことを決め、大学で発酵の更なる深い世界を学びました。
「自分で醤油とか、
もっと気軽に仕込めるような状況になってほしい。
もっと醤油が身近になれば。
買って当たり前じゃなく、
造ってみたいなって思ってもらえるようにしたいんです」
おばあちゃんとの記憶とともに身体に染み込んだ、揺るぎない美味しさを知っているからこそ、軸がある。たとえ、目に見えず、時にはやっかいな微生物だったとしても、その世界へ飛び込むぶれない眼差しがある。この、世代を越えて受け継がれんとしている美味しさを、地域の食の文化として、もっと認知されなければならないと思うのです。そうしてこそやっと伝統が継続されていくのだと思います。まずはどうか、芝山糀店の味噌や甘酒の美味しさに驚いてください。「残したい味だな」きっとそう思っていただけるはずです。